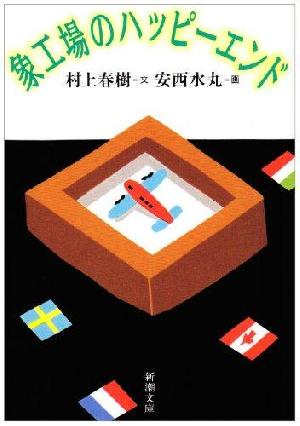ある種のコーヒーの飲み方について マスター 2004-02-25 15:17:00 No.123
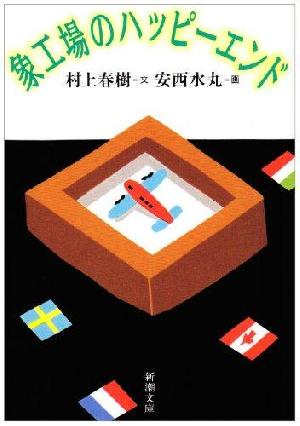
僕がはじめて一人で喫茶店に入ったのは17歳になったばかりの春だったと思う。家の方から疎水沿いに白川小道という平和な散歩道をのんびり歩いて行くと、赤レンガの壁が見える。GeorgesⅤ(ジョルジュサンク)という喫茶店だった。ショパンの恋人みたいな名前だった。油引きの床で、古い小さなピアノが置いてあった。今はその喫茶店はその場所にはないが、もしかしたらピアノだけはまだ置いてあるかもしれない。
ドアを開けると鐘の音がする。その辺に置いてある新聞とマッチを取って窓辺の席につく。僕はホットを注文し、ショート・ホープにマッチで火をつける。オレンジ色のマッチ箱だった。運ばれてきたコーヒーには春の空気とあわさった、優しい香りがあった。煙草の煙をゆっくりはきながら、少しクラクラして飲むコーヒーは大人の味がした。
ちょっと前、探し物をしていて物置をあさっていたらGeorgesⅤのマッチが大量に出てきた。50箱以上あった。そういえばよく行ったなあと思う。一人で行ったこともあったし、男二人で行ったこともあったし、女の子と二人で行ったこともあった。何を話してたかということは断片的によく覚えている。いずれにせよ、僕はほとんどホットを飲んだ。その頃のホットの飲み方はコーヒーの味というよりコーヒーのあるあたたかい風景を楽しむ飲み方だった。そんなふうなある種のコーヒーの飲み方について、村上春樹氏が文章を書いている。僕はこの文章がとても好きだ。少し引用する。
ある種のコーヒーの飲み方について
その午後にはウィントン・ケリーのピアノが流れていた。ウェイトレスが白いコーヒー・カップを僕の前に置いた。ぶ厚い、重いカップで、テーブルに置く時にカタンという気持の良い音がした。まるでプールの水底に落ちた小石のように、その音は僕の耳にずっと残っていた。僕は十六歳で、外は雨だった。
(中略)
天井に取りつけられたスピーカーからジャズが流れていた。目を閉じると、まっ暗な部屋に閉じこめられた小さな子供のような気持になった。そこにはいつもコーヒー・カップの親密な温もりがあり、少女たちの優しい香りがあった。
(中略)
僕の前にはあの思春期特有のキラキラと光る鏡があり、そこにはコーヒーを飲む僕の姿がくっきりと映し出されていた。そして僕の背後には四角く切り取られた小さな風景があった。コーヒーは闇のように黒く、ジャズの響きのように暖かかった。僕がその小さな世界を飲み干す時、風景が僕を祝福した。
(中略)
時には人生はカップ一杯のコーヒーがもたらす暖かさの問題、とリチャード・ブローティガンがどこかに書いていた。コーヒーを扱った文章の中でも、僕はこれがいちばん気に入っている。
―村上春樹著 象工場のハッピーエンド(新潮社)より―
17才の頃の僕にとっては、格言で人生の真理を説かれるより、カップ一杯のコーヒーの暖かさが必要であったし、多分今もこれからも不可欠なものであるはずだ。
- 365 image bbs Ver1.01 -